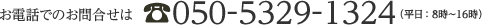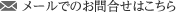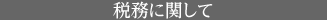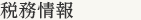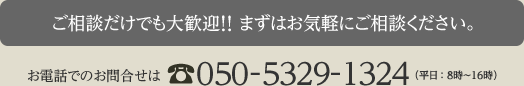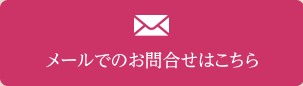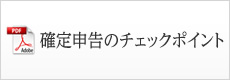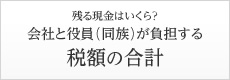生前贈与(現金)の選択肢
「一年の計は元旦にあり」とことわざにありますが、年が明けたばかりの1月中の取り組み方でこの1年の方向性が決まってしまうように思います。
昨年は相続税を補完する贈与税において大きな改正があり、それについては令和6年5月の通信でも取り上げましたが、その内容についての選択の期限が迫っておりますのでもう一度触れておきたいと思います。
改正の目玉は暦年課税制度における生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されたことでした。これは令和6年1月から行う贈与について適用され、令和9年から発生する相続に影響が出ることになります。つまり最長7年まで遡って行った贈与を相続時に戻し入れることになります。(ただし100万円の控除あり)
もうひとつの目玉は相続時精算課税制度の年間110万円の非課税枠が新設されたことです。
暦年課税制度と相続時精算課税制度は選択性になっており、何もしなければ暦年課税制度が適用され、相続時精算課税制度を選択するときには税務署に届出書の提出が必要になります(※)。また一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度には戻ることはできません。それではどちらを選択した方がいいのでしょうか。
①毎年110万円以下の金額しか贈与を行わない場合
→ 相続時精算課税制度を選択しましょう
それにより贈与をした金額は相続時に戻し入れる必要はありません
②贈与する人が元気で110万円以上の贈与も行いたい場合
→ 暦年課税制度のままでいきましょう。
110万円以上の贈与分については贈与税がかかりますが、年数が長いので贈与プランが立てやすいです
③相続人以外の人に贈与を行う場合
→ 暦年課税制度しか使えません。
直系尊属からの贈与は特例贈与財産となり税率が少し低くなっています
④贈与する人が元気では無い場合
→ 贈与をする金額でケースバイケースですが、
毎年の金額が110万円前後であれば相続時精算課税制度を選択しましょう
⑤将来値上がりが予測される不動産や株式を贈与したい場合
→ 相続時精算課税制度を選択しましょう。
この制度は贈与した分を相続時に持ち戻すことになりますが、その価額は贈与時の金額となりますので値上がりが期待できる財産については有効になります
相続は発生してしまうとその現状のみを受け入れることになりますが、贈与はある程度プランニングすることが可能です。贈与税は相続税の補完税と呼ばれていますが、プランニングによっては相続税を引き下げることも可能になりますので、贈与される人とよく話し合い節税を目的とした健全な贈与をしていただくことを願っております。
(※)相続時精算課税の届出は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署に提出します。(受贈者の戸籍謄本等の書類の添付が必要です)
← 一覧に戻る
※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております